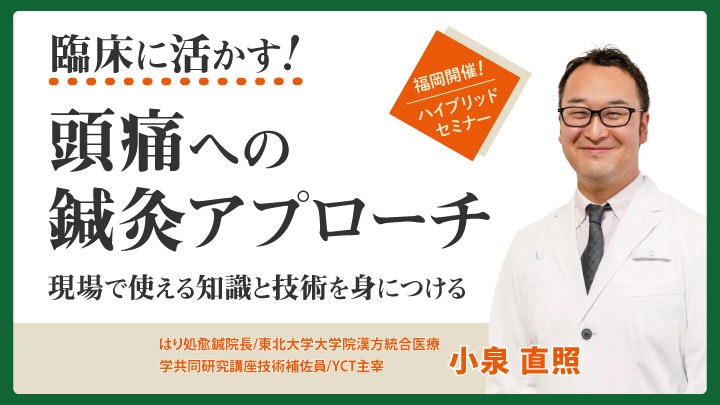はじめに
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、症状が現れにくく、それでいて人体最大の化学工場ともいえる働きを担っています。
右上腹部の横隔膜直下にあり、約1.5kgの重量を持ち、血液の約13%が常にここを流れています。
その機能は多岐にわたり、栄養代謝、解毒、胆汁の生成、血液貯蔵、ホルモン分解、体温維持にまで及びます。
一方で、肝臓の働きを補佐するのが「胆嚢」です。
胆嚢は肝の下面に付着し、胆汁を一時的に貯蔵して濃縮し、脂肪の消化を助けます。
これら肝胆系は、東洋医学においても「気の流れ」と「情動の安定」に深く関係するとされ、
臨床では右肩のこり、側腹部の張り、目の疲れ、怒りやイライラ感といった症状にも影響します。
鍼灸師にとって、肝・胆の正確な位置と構造を理解することは、
単に臓器損傷を避けるためだけでなく、代謝・循環・情動調整を支える根拠を得るための鍵となります。
1️⃣ 肝臓の位置と構造
● 解剖学的位置
肝臓は右上腹部の大部分を占め、横隔膜のすぐ下に位置します。
右葉と左葉に分かれ、さらに機能的には8つの区域(クイノー分類)に区分されます。
- 上端:第5肋間〜右乳頭線上
- 下端:右肋弓下〜左季肋下
- 背側:右腎・副腎・下大静脈
- 前面:横隔膜・腹壁・肋骨
- 支配神経:迷走神経(副交感)・大内臓神経(交感)
肝臓は膜構造(グリソン鞘)で被われ、肝動脈・門脈・胆管が一束となって出入りします。
この「肝門部」は胆嚢・膵頭部とも密接であり、胆汁や膵液の流れを統合的に理解する必要があります。
● 肝臓の機能(臨床的視点)
- 代謝機能:糖・脂質・タンパク質の合成と分解
- 解毒作用:薬物・アルコール・アンモニアの処理
- 胆汁生成:脂肪分解と老廃物排泄
- 血液貯蔵:循環調整・体温維持
- ホルモン分解:ストレス反応・免疫調整への影響
臨床的には、慢性疲労・肩背部の重だるさ・眼精疲労・ストレスによる食欲低下などの背景に、肝血流低下が関係することが多くあります。
2️⃣ 胆嚢の位置と構造
胆嚢は肝右葉の下面、肝臓と十二指腸の間に位置し、長さ約7〜10cmの袋状臓器です。
肝臓で生成された胆汁を貯蔵し、脂肪が小腸に入ると収縮して胆汁を排出します。
- 位置の目安:第9肋軟骨尖端(右乳頭線上)
- 支配神経:迷走神経・右横隔神経枝・交感線維(T7〜T9)
- 臨床的注意点:過度な右季肋部刺鍼で胆嚢穿刺の危険(特に痩身者)
胆嚢炎や胆石症では、右肩や肩甲間部への放散痛(胆道反射痛)が生じます。
これは、横隔膜と肩周囲の感覚が同じ神経(C3〜C5)で支配されているためであり、鍼灸的にも重要な関連です。
3️⃣ 肝・胆と関連する主要経穴
| 経穴名 | 経絡 | 解剖位置 | 主な作用 |
|---|---|---|---|
| 期門(LR14) | 肝経の募穴 | 乳頭直下、第6肋間 | 肝気鬱結・胸脇苦満・右上腹部痛 |
| 日月(GB24) | 胆経の募穴 | 第7肋間、乳頭線上 | 胆嚢疾患・右肩のこり・食欲不振 |
| 陽陵泉(GB34) | 胆経合穴 | 腓骨頭前下方 | 筋肉の痙攣・胆の働きの調整 |
| 太衝(LR3) | 肝経原穴 | 足背、第1・2中足骨間 | 自律神経調整・精神安定 |
| 章門(LR13) | 脾の募穴・肝経 | 第11肋骨先端下 | 肝脾不和・腹満・消化不良 |
これらの経穴は、**「肝胆の連動」と「気の滞り」**を解くための基本ルートであり、
右季肋下の緊張や情動ストレスを整えるうえで最もよく使われます。
4️⃣ 鍼灸施術と安全の要点
- 右上腹部への刺鍼は浅めに・外斜刺を原則に
→ 肝臓は大きく、吸気で前下方に動くため、深刺で肝被膜を刺激する危険あり。 - 経絡ラインに沿って間接的にアプローチ
→ 期門・日月・章門・陽陵泉を組み合わせて「経絡上で肝胆を動かす」。 - 背部兪穴(肝兪・胆兪)からの補助刺激
→ 第9・10胸椎下縁に位置し、肝臓の循環を高める。 - ストレス系症状には太衝・内関の併用
→ 自律神経の調整と感情安定に有効。
5️⃣ 臨床応用
- 慢性疲労・ストレス性消化不良
→ 肝経(期門・太衝)+脾経(章門・足三里)
→ 「肝脾不和」の調整。 - 右肩こり・胆道反射痛
→ 日月・陽陵泉・肩井の併用。 - 月経前緊張・イライラ・眼精疲労
→ 太衝・肝兪・百会の組み合わせで血流と気の流れを整える。
まとめ
肝臓と胆嚢は、代謝と循環、そして情動バランスを支える中心的な臓器です。
肝は「貯蔵と解毒の臓」、胆は「決断と排出の臓」として機能し、
互いに連携して生命活動を維持しています。
鍼灸師がこれらの構造を理解することで、右季肋部の刺鍼を安全に行うだけでなく、
内臓反射や経絡の連動を立体的に捉えることができます。
特に期門や日月の刺鍼では、呼吸に合わせて角度を外方へ逃すなど、解剖に基づいた操作が欠かせません。
さらに、肝胆の理解は臨床的に「ストレス・自律神経・循環・感情」といったテーマにも波及します。
体だけでなく心の緊張を解き、患者が深く呼吸できる状態へ導く——それが、肝胆を理解した鍼灸師の真価です。
次回は、膵臓と十二指腸の構造 ― 消化酵素と内分泌の二重性を解剖学的に探ります。
👉鍼灸学校で解剖学と生理学を学ぶ重要性:鍼灸師としての基礎を築く知識とは?
👉鍼灸師の先輩が実践!経穴を楽しく覚える8つの効果的な学習法
👉鍼灸師のための生理学総論─恒常性維持と鍼刺激の生理学的理解