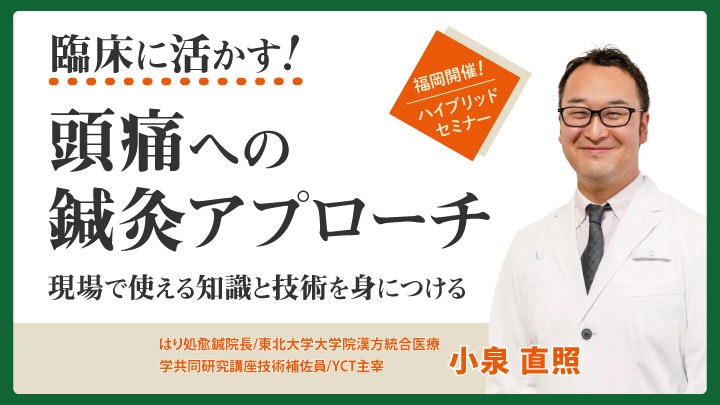はじめに
鍼灸臨床で腹部の施術を行うとき、最も意識すべき臓器が「胃」と「膵臓」です。
どちらも消化機能の中心であり、内臓のなかでも特に血流が豊富で、神経支配も複雑です。
また、胃は鍼灸で最も頻用されるツボ群の直下に位置し、中脘・梁門・不容・足三里など、胃経のツボとの関係が極めて深い臓器です。
膵臓は胃の後方、後腹膜に位置するため、腹部からは直接触れません。
しかしその解剖を理解することで、胃後壁への安全な刺鍼深度、背部からの膵部アプローチ(膵兪・脾兪など)を的確に判断できます。
現代では、食生活の乱れやストレスによる消化機能の低下、慢性的な膵臓疲労(いわゆる膵機能低下症)が増加しています。
鍼灸師が臓器の位置と構造を正確に理解すれば、腹部施術の安全性だけでなく、消化不良・胃の重さ・倦怠感といった日常的な不定愁訴にも、より具体的なアプローチが可能になります。
1️⃣ 胃の位置と構造
● 解剖学的位置
胃は横隔膜のすぐ下、みぞおち(心窩部)の左寄りに位置します。
上部は食道から連続し(噴門部)、左上に膨らんだ胃底部、中央の胃体部、そして右下の幽門部へとつながります。
幽門の先は十二指腸に続き、ここで膵液と胆汁が混ざり、消化が進みます。
- 高さの目安:立位で第6肋骨下縁〜第1腰椎前方
- 前方臓器:肝左葉、腹壁
- 後方臓器:膵臓、左腎、脾臓
- 支配神経:迷走神経(副交感)・内臓神経(交感)
- 主血管:左胃動脈・右胃動脈・短胃動脈
● 胃の生理的可動
胃は、姿勢・呼吸・食事によって位置が変化します。
- 空腹時:胃体部が縮小し、みぞおち奥に収まる
- 食後:胃底部が左上方に膨張し、横隔膜を押し上げる
- 仰臥位:胃の後壁が脊柱に近づく
したがって、中脘(CV12)・梁門(ST21)への刺鍼では、体位・呼吸・空腹時の確認が不可欠です。
2️⃣ 膵臓の構造と位置
膵臓は胃の後ろに横たわる細長い臓器で、頭部・体部・尾部に分かれます。
- 頭部:十二指腸の内側に抱かれる
- 体部:胃の裏側で大動脈の前を横断
- 尾部:脾門(脾臓の根元)に達する
膵臓は、食べ物の消化を助ける膵液(外分泌)と、血糖を調整するインスリン・グルカゴン(内分泌)を分泌します。
すなわち、消化と代謝の両方に関与する、極めて重要な臓器です。
- 支配神経:迷走神経・大内臓神経(交感)
- 主要血管:脾動脈・上腸間膜動脈
膵臓は後腹膜臓器のため、鍼による直接刺激は困難です。
ただし、中脘からやや左下の刺鍼角度を浅く調整することで、胃後壁と膵体部の間の緊張を和らげることが可能です。
3️⃣ 胃と膵臓に関連する主要経穴
| 経穴名 | 経絡 | 解剖位置 | 主な作用 |
|---|---|---|---|
| 中脘(CV12) | 任脈・胃経交会穴 | 胃体部前面直上 | 胃もたれ・食欲不振・胃炎 |
| 梁門(ST21) | 足の陽明胃経 | 臍上2寸・中脘の外方2寸 | 胃下垂・食後の重さ |
| 不容(ST19) | 胃経 | 胸骨下端と臍の中間・中脘の上方 | 胃酸過多・吐き気 |
| 足三里(ST36) | 胃経 | 膝下3寸・脛骨前稜外側 | 消化機能促進・全身調整 |
| 胃兪(BL21) | 膀胱経 | 第12胸椎棘突起下縁 | 背部からの胃部調整 |
これらのツボは、胃・膵臓・自律神経を同時に調整できる「前後対応の黄金ライン」です。
4️⃣ 鍼灸施術での注意点
- 中脘・梁門は深刺しすぎると膵体部に到達する恐れがあるため、0.8〜1.2寸の範囲で垂直または軽い斜刺。
- 食後30分以内の腹部施術は避ける。
- 呼吸に合わせ、吸気で横隔膜が下がるタイミングに合わせて刺入すると安全。
- 背部(胃兪)はやや外斜刺、膵兪(脾兪や胃兪の間)への施術では深度を浅めに保つ。
5️⃣ 臨床応用:胃・膵臓と全身の関連
- ストレス性胃炎・食欲不振
→ 迷走神経・肝経の緊張による胃の血流低下。
→ 中脘+太衝+足三里の組み合わせで副交感神経を活性化。 - 胃下垂・腹部の重だるさ
→ 腹壁筋・腸腰筋の緊張緩和が有効。
→ 梁門・天枢+大巨+足三里。 - 膵疲労・低血糖傾向
→ 足三里・膵兪・志室を併用し、代謝機能を底上げ。 - 暴飲暴食後の胃痛
→ 胃酸分泌過多を抑える目的で不容+中脘+内関。
まとめ
胃と膵臓は、鍼灸施術で最も頻繁に意識すべき臓器のひとつです。
解剖学的に見ると、胃は腹壁直下の浅い位置にあり、膵臓はその背面に密着して存在します。
両者は構造的に密接に連動しており、消化・吸収・代謝を一体として担っています。
鍼灸師がこれらの臓器を理解することは、安全な刺鍼だけでなく、腹部全体の“動き”を感じ取るうえでも重要です。
ツボを刺すというより、「その奥にある胃と膵臓を感じながら操作する」意識が、安全性と効果の両立を生みます。
今後の学びでは、腹腔の奥にある臓器がどのように支え合い、経絡と交わるのかをさらに掘り下げていきます。
次回は「肝臓と胆嚢の構造 ― 代謝と感情をつなぐ臓器」を解剖学的に探ります。
👉鍼灸学校で解剖学と生理学を学ぶ重要性:鍼灸師としての基礎を築く知識とは?
👉鍼灸師の先輩が実践!経穴を楽しく覚える8つの効果的な学習法
👉鍼灸師のための生理学総論─恒常性維持と鍼刺激の生理学的理解