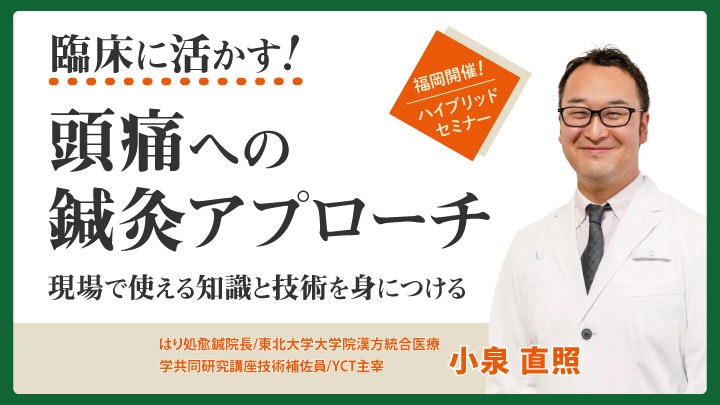はじめに
膵臓と十二指腸は、人体のなかでも“消化と代謝の交差点”ともいえる臓器群です。
膵臓は胃の背後、腹部の深い位置に横たわり、消化酵素を分泌する外分泌機能と、血糖を調整する内分泌機能という二つの役割を同時に担っています。
一方、十二指腸は胃から小腸への入口であり、胆汁と膵液が流れ込む重要な消化の起点です。
鍼灸師にとって、膵臓と十二指腸の解剖学的理解は、中脘や巨闕といった腹部経穴の安全な深度を知ることに直結します。
また、近年注目される「自律神経と代謝機能の関連」や、「ストレスによる膵疲労・血糖変動」などを考える上でも、この領域の知識は不可欠です。
臨床では、慢性的な疲労感、胃の不快感、食後の眠気、冷えなどの背景に、膵臓や十二指腸の血流・神経バランスの乱れが潜むケースが少なくありません。
本記事では、鍼灸師が「安全に刺し、内臓を感じ、代謝を調える」ために必要な膵臓・十二指腸の構造とツボの関係を詳しく解説します。
1️⃣ 膵臓の位置と構造
● 位置
膵臓は胃の後方、後腹膜に固定された細長い臓器で、頭部・体部・尾部に分けられます。
- 頭部:十二指腸の内側に包まれる
- 体部:腹部中央で大動脈の前方を横断
- 尾部:左上方に向かい、脾門(脾臓の根元)に接する
成人では、おおよそ第1〜2腰椎の高さ。胃体部や中脘直下に重なります。
● 形態と組織
膵臓は外分泌腺(膵腺房)と内分泌腺(ランゲルハンス島)で構成されます。
- 外分泌腺:膵液を膵管を通じて十二指腸へ分泌(アミラーゼ・リパーゼ・トリプシン)
- 内分泌腺:インスリン(β細胞)・グルカゴン(α細胞)・ソマトスタチン(δ細胞)などを分泌
この構造が、膵臓を「消化」と「血糖」の両面から制御する独自の臓器にしています。
2️⃣ 十二指腸の構造と膵臓との関係
十二指腸は長さ約25cmのC字型の管で、胃幽門部から続き、膵頭部を包み込むように走行します。
その内側に、膵管と胆管が合流して開口する「ファーター乳頭(十二指腸乳頭)」があります。
ここから、胆汁と膵液が同時に排出され、脂質・タンパク質の分解が始まります。
- 上部(球部):胃幽門と接続。潰瘍が多発する部位。
- 下降部:膵頭に沿って下行。胆膵開口部を含む。
- 水平部・上行部:腹部大動脈と上腸間膜動脈の間を通過。
この複雑な立体構造のため、十二指腸周囲への深刺は臓器損傷のリスクが最も高い領域です。
3️⃣ 神経支配と血流
| 系統 | 内容 | 鍼灸的意義 |
|---|---|---|
| 交感神経 | 胸髄T6〜T10からの大内臓神経 | ストレス時の膵酵素抑制・血流低下 |
| 副交感神経 | 迷走神経 | 膵液分泌促進・胃腸運動活性化 |
| 血流 | 脾動脈・上腸間膜動脈・膵十二指腸動脈 | 腹部温灸・経絡刺激による循環改善が有効 |
膵臓は交感・副交感の両支配を強く受ける臓器であり、自律神経の影響が最も現れやすい内臓の一つです。
そのため、鍼灸では内臓機能だけでなく、自律神経のトーン(緊張度)を意識した施術が求められます。
4️⃣ 関連する主要経穴
| 経穴名 | 経絡 | 解剖位置 | 主な作用 |
|---|---|---|---|
| 中脘(CV12) | 任脈・胃経 | 胃体部と膵体部の間 | 胃炎・膵機能低下・食欲不振 |
| 巨闕(CV14) | 任脈 | 心窩部・胃上部前面 | 胃痙攣・ストレス性消化不良 |
| 脾兪(BL20) | 膀胱経 | 第11胸椎棘突起下縁 | 消化吸収・内分泌調整 |
| 胃兪(BL21) | 膀胱経 | 第12胸椎棘突起下縁 | 胃機能調整・背部循環促進 |
| 足三里(ST36) | 胃経 | 膝下3寸・脛骨外側 | 消化機能・免疫強化 |
これらのツボは、前面と背面から膵臓を“挟み込む”ように作用するため、局所刺鍼が難しい臓器の機能調整に最適です。
5️⃣ 臨床応用
- 慢性疲労・低血糖傾向
→ 足三里・脾兪・中脘を用いて膵内分泌の活性化を図る。 - ストレス性消化不良・胃痛
→ 巨闕・内関・足三里で迷走神経トーンを高め、消化促進。 - 食後の倦怠感・血糖変動
→ 膵の循環促進を目的に、背部の膵兪(脾兪と胃兪の間)を軽刺激。 - 冷え・胃の重さ・緊張型腹部
→ 腹部温灸+中脘刺鍼で腹膜反射を緩和。
まとめ
膵臓と十二指腸は、単なる消化器官ではなく、代謝・自律神経・免疫にまたがる多機能臓器です。
その構造は複雑で、特に膵体部や十二指腸下降部周辺は鍼灸施術で最も慎重な領域といえます。
しかし、正確な位置関係を理解すれば、鍼灸による“間接的な刺激”でこれらの臓器を安全に調整できます。
膵臓の外分泌は「胃と肝」、内分泌は「脾と腎」とも密接に連携しています。
したがって、経絡的にも任脈・胃経・脾経・肝経の協調が重要です。
鍼灸師が臓器を“解剖の形として理解し、機能として感じる”ことは、
安全な刺鍼と高精度な経絡治療を両立させるための根幹となります。
次回は、「小腸と大腸 ― 吸収と排泄を司る臓器構造」を詳しく解剖します。
👉鍼灸学校で解剖学と生理学を学ぶ重要性:鍼灸師としての基礎を築く知識とは?
👉鍼灸師の先輩が実践!経穴を楽しく覚える8つの効果的な学習法
👉鍼灸師のための生理学総論─恒常性維持と鍼刺激の生理学的理解