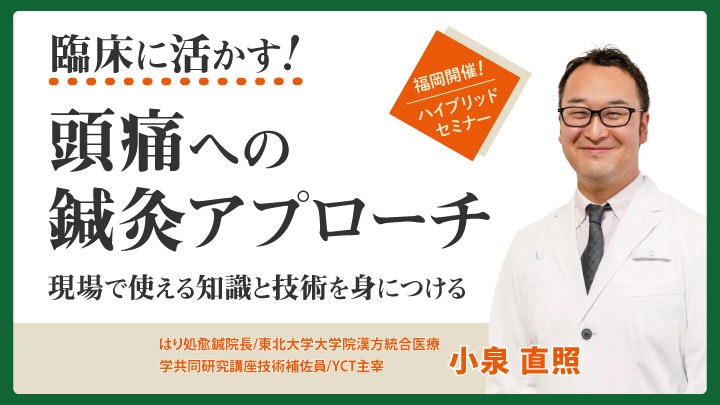はじめに
肺は、呼吸を通じて酸素を取り入れ、二酸化炭素を排出する臓器であり、
東洋医学では「気を司る臓」として全身のエネルギー循環に深く関わります。
現代解剖学では、肺は胸腔の左右に位置し、心臓を囲むように配置されています。
呼吸のたびに横隔膜が上下し、肋骨が広がることで空気が出入りします。
この機械的な運動を支えるのが自律神経系(交感・副交感)であり、
ストレス・姿勢・感情の変化によっても呼吸リズムは簡単に乱れます。
鍼灸師にとって肺の理解は、咳や喘息だけでなく、
気虚・息切れ・自律神経失調・うつ・不眠・免疫低下といった幅広い症状へのアプローチの基盤となります。
本記事では、肺と呼吸器の構造を立体的に理解し、安全な胸部刺鍼と臨床応用を解説します。
1️⃣ 肺の構造と位置
肺は左右非対称のスポンジ状臓器で、右肺は3葉(上・中・下葉)、左肺は2葉(心臓にスペースを譲るため)で構成されています。
- 位置:鎖骨上端から第10肋骨レベルまで
- 上端(肺尖):鎖骨の上方約2〜3cm
- 下端:安静呼気時で第6肋骨中線、深呼吸で第10肋骨まで下降
- 後面:肋骨と接し、背部の肺兪(BL13)付近に位置
- 支配神経:迷走神経(副交感)・胸髄(T2〜T6)由来の交感神経
胸腔内での肺の動きは、横隔膜と肋間筋によって調整されます。
そのため、呼吸器系の治療では「胸郭の柔軟性」と「横隔膜の可動性」が重要な視点となります。
2️⃣ 気道と呼吸運動のメカニズム
| 部位 | 役割 | 鍼灸的関連 |
|---|---|---|
| 鼻腔・咽頭・喉頭 | 空気の加温・加湿・声帯振動 | 咽喉不快・発声疲労に対する頸部刺激 |
| 気管 | 空気の通り道(長さ約10cm) | 喉のつまり感・浅呼吸の背景 |
| 気管支 | 右主気管支は太く短い | 呼吸音異常・喘息反応部位 |
| 肺胞 | ガス交換の場(表面積70㎡) | 血流・酸素運搬と「気血」の象徴 |
呼吸運動は、吸気=横隔膜下降+肋骨挙上、呼気=筋弛緩による弾性収縮で行われます。
この際、横隔膜の緊張や肋間筋の硬さがあると呼吸が浅くなり、交感神経優位となって不安・動悸・不眠などを招きます。
3️⃣ 肺と関連する主要経穴
| 経穴名 | 経絡 | 位置 | 主な作用 |
|---|---|---|---|
| 中府(LU1) | 肺経の募穴・太陰肺経 | 鎖骨下窩外方、第1肋間 | 咳・胸の詰まり・浅呼吸 |
| 雲門(LU2) | 肺経 | 鎖骨外端下方の凹み | 胸肩の緊張・呼吸改善 |
| 肺兪(BL13) | 膀胱経 | 第3胸椎棘突起下縁 | 咳・喘息・免疫調整 |
| 天突(CV22) | 任脈 | 胸骨上窩中央 | 喉の閉塞感・発声疲労 |
| 列缺(LU7) | 肺経 絡穴 | 手首橈側、茎状突起の上方 | 呼吸調整・頭頸部循環改善 |
これらの経穴を「胸前+背部+上肢」で組み合わせると、肺気の出入りを多層的に調整できます。
4️⃣ 鍼灸施術と安全の要点
- 胸部刺鍼の深度管理
→ 中府・雲門は0.3〜0.5寸の浅刺が基本。深刺は気胸の危険があるため厳禁。 - 背部施術での呼吸同調
→ 肺兪・厥陰兪への刺鍼は吸気で刺入、呼気で抜鍼すると安全。 - 温灸・吸角(カッピング)との併用
→ 背部循環促進と免疫活性化に有効。風邪や喘息の慢性期に用いる。 - 自律神経調整としての呼吸誘導
→ 刺鍼中に深呼吸を促すことで、迷走神経を活性化し副交感神経を優位化。
5️⃣ 臨床応用
- 咳・喘息・胸の圧迫感
→ 中府+肺兪+列缺で気道の通りを改善。 - 息切れ・疲労・冷え
→ 雲門+膻中+太淵で呼吸筋と循環を補う。 - ストレス・不安・不眠
→ 肺経+心包経(内関・神門)の併用で自律神経を整える。 - 風邪予防・免疫向上
→ 肺兪+風門への温灸刺激で「衛気」を強化。
まとめ
肺は、単なる呼吸器官ではなく、生命エネルギー(気)を外界と交換するゲートです。
呼吸の深さは心の安定とも直結し、浅い呼吸は不安・緊張・倦怠として現れます。
鍼灸師が肺の解剖を理解することは、胸部刺鍼の安全確保だけでなく、
「呼吸=気の流れ」を臨床的に感じ取るための第一歩です。
中府や肺兪は、身体の「入り口と出口」をつなぐ要点であり、呼吸を整えることは即ち全身の気血を整えることにつながります。
次回は、「脾臓と消化吸収 ― 気血生化の中心」をテーマに、
食とエネルギー代謝の仕組みを鍼灸的視点から掘り下げます。
👉鍼灸学校で解剖学と生理学を学ぶ重要性:鍼灸師としての基礎を築く知識とは?
👉鍼灸師の先輩が実践!経穴を楽しく覚える8つの効果的な学習法
👉鍼灸師のための生理学総論─恒常性維持と鍼刺激の生理学的理解