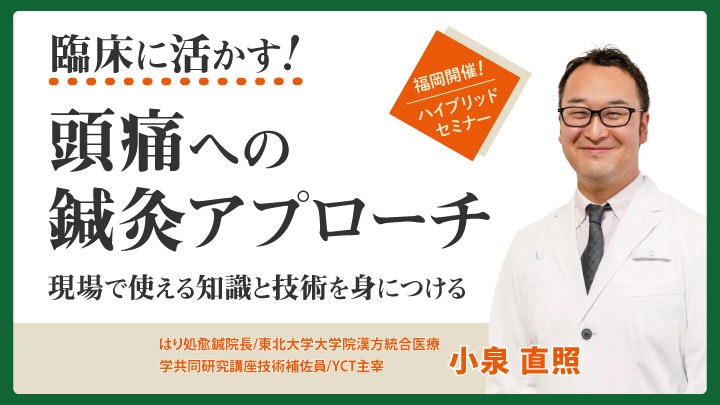はじめに
鍼灸師にとって、筋肉や経穴の位置関係を把握することはもちろん重要ですが、
実際の臨床では「その下に何があるのか」を理解しているかどうかが、安全性を大きく左右します。
胸腹部の刺鍼では、呼吸運動に伴う横隔膜の可動性、腹壁の厚み、そして内臓の位置関係を誤解すると、思わぬ臓器損傷を招く危険があります。特に、鍼灸師が日常的に扱う中脘(CV12)・天枢(ST25)・期門(LR14)・巨闕(CV14)といった経穴は、いずれも臓器直上または近接部に位置します。
加えて、近年は施術の対象が多様化し、腹部の美容鍼、胃腸機能改善、冷え性対策などで腹部刺鍼の機会が増えています。その一方で、深刺や角度の誤りによる臓器損傷リスクも指摘されています。したがって、鍼灸師が安全かつ効果的に施術を行うには、臓器の位置と動き、膜構造の理解が必須です。本記事では、胸腔と腹腔を分ける「横隔膜」から始まり、臓器を包む「腹膜」の仕組み、主要臓器の位置関係を立体的に学びます。
1️⃣ 胸腹部を二つの空間として理解する
人体の体幹内部は、大きく 「胸腔(きょうくう)」と「腹腔(ふくくう)」 に分かれています。
これらを隔てているのが、呼吸の主役でもある 横隔膜(おうかくまく) です。
- 胸腔:肺と心臓を収める空間。肋骨に囲まれ、陰圧で保たれる。
- 腹腔:胃・肝臓・腸・脾臓・膵臓・腎臓などが納まる。陽圧空間で、腹圧が維持されている。
横隔膜は吸気で下降し、腹腔内圧を高めます。つまり、呼吸運動によって内臓全体が上下方向に動くのです。
鍼灸師は、横隔膜の可動性を理解することで、中脘・鳩尾・期門などの刺鍼深度をより安全に設定できます。
2️⃣ 腹膜とは何か ― 臓器を包む「滑る膜」
腹腔内臓器の多くは、「腹膜(peritoneum)」という薄い膜で覆われています。
腹膜は「臓側腹膜」と「壁側腹膜」に分かれ、その間に形成される空間を「腹膜腔」と呼びます。
● 壁側腹膜
腹壁や横隔膜、骨盤壁の内側を覆う。
→ 鍼で刺入する際、まず通過する「壁側層」でもある。
● 臓側腹膜
胃・腸・肝などの臓器表面を包む。
→ この層を介して臓器が滑らかに動く。
● 腹膜間の“反転”
壁側腹膜が臓器を包み込み、再び壁へ戻ることで「小網」「大網」「間膜」などの構造をつくる。
この反転のラインが、内臓の“吊り下げ構造”を形づくる重要ポイント。
3️⃣ 臓器の位置関係を立体的に把握する
臓器は平面的ではなく、前後・上下・左右に層を成して配置されています。
ここを「断面図のイメージ」で理解することが、鍼灸安全の第一歩です。
| 層構造 | 主な臓器 | 鍼灸臨床で注意すべき点 |
|---|---|---|
| 最前層 | 腹直筋・腹横筋・腹膜前脂肪 | 腹壁厚により刺鍼深度が変化する(肥満・瘦身で差大) |
| 中層 | 胃・肝・脾・小腸・結腸 | 呼吸・食後で位置が変わるため、臨床時は体位と空腹時を確認 |
| 後層 | 腎・膵・副腎・大動脈 | 腰背部からの深刺に注意。腎兪・志室などの刺鍼深度管理が重要 |
4️⃣ 主要臓器の位置と深度感覚
● 胃
- 左季肋下(みぞおち左側)にあり、肋骨弓に隠れるように存在。
- 深刺で膵臓と接する可能性あり。
- 経穴:中脘(CV12)、梁門(ST21)、不容(ST19)
● 肝臓
- 右季肋部全体を覆う最大臓器。右横隔膜下に位置。
- 刺鍼時は右上腹部で深度を制御。
- 経穴:期門(LR14)、日月(GB24)
● 脾臓
- 左後側に位置し、肋骨に守られる。
- 左季肋下の刺鍼では、角度を内方にせず外斜刺が原則。
- 経穴:脾兪(BL20)、章門(LR13)
● 腎臓
- 第12胸椎〜第3腰椎の高さ。右腎はやや下位に位置。
- 背部刺鍼(腎兪・志室)では刺入角度を浅く、外下方へ。
5️⃣ 鍼灸師が知っておくべき「安全刺鍼三原則」
(1)臓器の可動を想定する
呼吸・姿勢・食後状態で、臓器の高さは最大3〜5cm変化します。
→ 鍼は“臓器が動く空間”を避けること。
(2)腹壁の厚みを測る感覚を持つ
特に腹部は、筋肉・脂肪・腹膜前層の厚みが個人差大。
→ 指圧・把握で「抵抗の変化」を読むことが重要。
(3)刺入方向は“内臓に向けない”
特に季肋下・下腹部は、角度が臓器へ直進しやすい。
→ 外斜刺・横刺を基本とし、吸気時に操作するのが安全。
6️⃣ 臓器と経穴の対応関係(鍼灸視点のマップ)
| 臓器 | 経絡・代表経穴 | 解剖的関連 | 臨床的効果 |
|---|---|---|---|
| 胃 | 足の陽明胃経(中脘・梁門・足三里) | 胃体〜幽門部 | 消化促進・胃下垂改善 |
| 肝 | 足の厥陰肝経(期門・太衝) | 右季肋下・胆嚢近接 | 肝気鬱結・右肩痛 |
| 脾 | 足の太陰脾経(章門・血海) | 左腹側後部 | 消化吸収・血液生成 |
| 腎 | 足の少陰腎経(腎兪・志室・太渓) | 後腹膜 | 冷え・疲労・ホルモン調整 |
| 心 | 手の少陰心経(巨闕・神門) | 前縦隔中央 | 動悸・精神安定 |
| 肺 | 手の太陰肺経(中府・肺兪) | 胸郭上部 | 呼吸循環調整 |
まとめ
胸腹部の内臓配置と腹膜構造を理解することは、鍼灸師にとって安全で精度の高い施術の第一歩です。
臓器は単なる「中身」ではなく、呼吸・姿勢・血流・筋膜の動きと連動し、日々位置を変化させています。
臓器の位置を正確にイメージできることは、
・深刺事故の防止
・ツボの立体的理解
・経絡走行の裏付け
のすべてに直結します。
さらに、臓器の理解は安全のためだけでなく、施術の質を高めるための感覚訓練にもなります。
たとえば、胃や肝の位置を意識して手技を行うことで、腹部の緊張や内臓下垂、消化不良に対してより的確なアプローチが可能になります。
今後の臨床において、鍼灸師は「皮下の解剖」だけでなく「臓器の地図」を頭に描きながら施術することが求められます。
次回は、臓器理解の第一歩として「胃と膵臓の構造・位置・支配神経」を詳しく取り上げ、臨床とのつながりを解説します。
👉鍼灸学校で解剖学と生理学を学ぶ重要性:鍼灸師としての基礎を築く知識とは?
👉鍼灸師の先輩が実践!経穴を楽しく覚える8つの効果的な学習法
👉鍼灸師のための生理学総論─恒常性維持と鍼刺激の生理学的理解