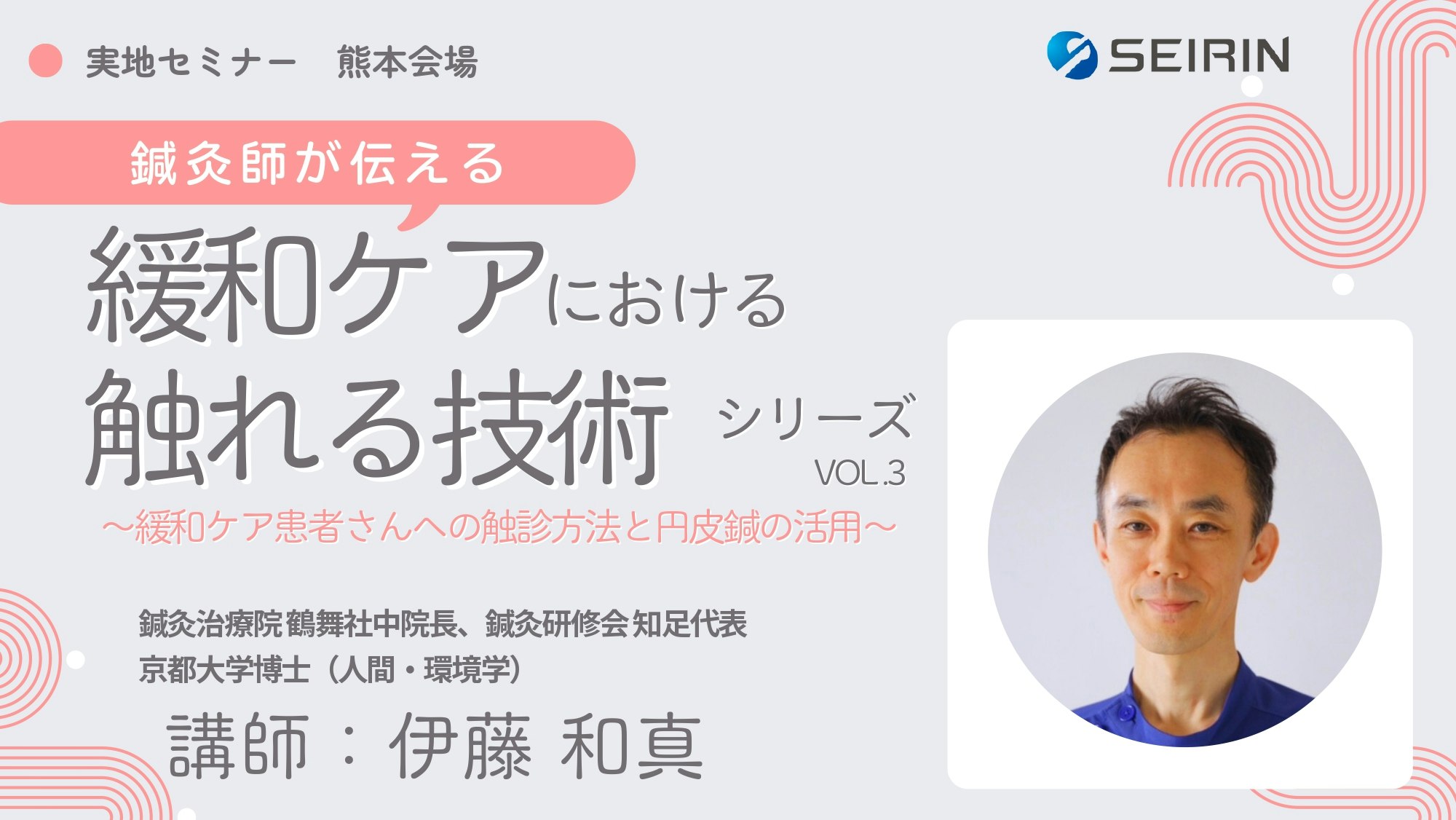はじめに:セロトニンは“幸福物質”だけではない
「セロトニン=幸せホルモン」として知られますが、その役割は気分調整にとどまりません。
痛みの制御、睡眠の質、自律神経バランス、腸機能などにも深く関与する、極めて多機能な神経伝達物質です。
鍼灸は、こうしたセロトニンの分泌・再取り込み・受容体活性に影響を与えることが研究で示唆されています。
本記事では、セロトニンと鍼灸の関係を、生理学・神経科学の視点から詳しく解説します。
セロトニンの基礎生理|どこで作られ、どう働くか?
| 分布部位 | 特徴 | 関与する機能 |
|---|---|---|
| 中枢神経(脳幹・縫線核) | 約2%を占める | 気分調整、睡眠、痛覚、体温 |
| 腸管内分泌細胞 | 約90%を産生 | 腸管蠕動、炎症制御 |
| 血小板 | 約8% | 血管収縮・止血調整 |
中枢では、縫線核(raphe nuclei)からの投射を通じて、大脳皮質・扁桃体・視床下部などへ影響を与えます。
腸では腸クロム親和性細胞がセロトニンを産生し、自律神経系と連携して腸の運動・免疫にも関与しています。
鍼灸がセロトニン系に及ぼす影響
① 縫線核のセロトニン放出を促進
鍼刺激は、百会・神門・足三里などの経穴刺激により、迷走神経→視床下部→縫線核ルートを介して、脳内のセロトニン放出を促進するとされます。
これは、抗うつ効果・鎮痛効果・自律神経調整の基盤となる神経経路です。
② 腸内セロトニン分泌と腸脳相関の調整
鍼灸は、腸の運動を整えることで腸内クロム親和性細胞のセロトニン産生を安定化させます。
これは「腸脳相関(gut-brain axis)」を通じて、感情や免疫の調整にも影響を与える要素です。
③ セロトニン受容体(5-HT1Aなど)の感受性向上
鍼灸は、セロトニンそのものの量だけでなく、受容体の機能調整(特に5-HT1A, 5-HT2Cなど)を通じて、
脳内の興奮性—抑制性バランスを整える働きも示唆されています。
鍼灸の適応が期待されるセロトニン関連症状
| 症状・疾患 | セロトニンとの関係 | 鍼灸の作用機序 |
|---|---|---|
| うつ病・不安障害 | セロトニン枯渇/受容体機能低下 | 中枢投射系の調整(百会・神門) |
| IBS(過敏性腸症候群) | 腸内セロトニン過多 or 不足 | 腸管神経調整(足三里・中脘) |
| 片頭痛 | 5-HT1B/1D受容体の異常反応 | 鍼刺激による血管収縮と鎮痛調整 |
| PMS(月経前症候群) | 月経周期に伴うセロトニン変動 | 自律神経系+視床下部調整 |
主に使用される経穴とその意図
| 経穴 | 主な効果 |
|---|---|
| 百会(ひゃくえ) | 縫線核系活性化、気分の安定 |
| 神門(しんもん) | 扁桃体の過活動抑制、抗不安作用 |
| 足三里(あしさんり) | 腸機能の調整と自律神経安定化 |
| 太衝(たいしょう) | イライラ・焦燥の緩和、セロトニン受容体活性化 |
| 中脘(ちゅうかん) | 胃腸の蠕動調整と消化管セロトニンへの影響 |
注意点と臨床上の配慮
- セロトニン系は抗うつ薬(SSRI・SNRI)との併用時に過剰刺激になる可能性もあるため、既存治療との慎重な併用判断が必要です
- 腸内セロトニンの変動には食事・腸内細菌環境・ストレスも大きく関与するため、生活指導とのセット対応が効果的です
まとめ
セロトニンは、痛み・気分・自律神経という多領域にわたって調整機能を担う“神経系のハブ”のような存在です。
鍼灸は、これらの神経系ルートに対して非侵襲的かつ多面的に作用し、セロトニン系の機能正常化を支援します。
とくに、薬物療法だけでは十分な効果が得られない患者層に対し、鍼灸は補完的介入手段として有用な可能性を示しています。