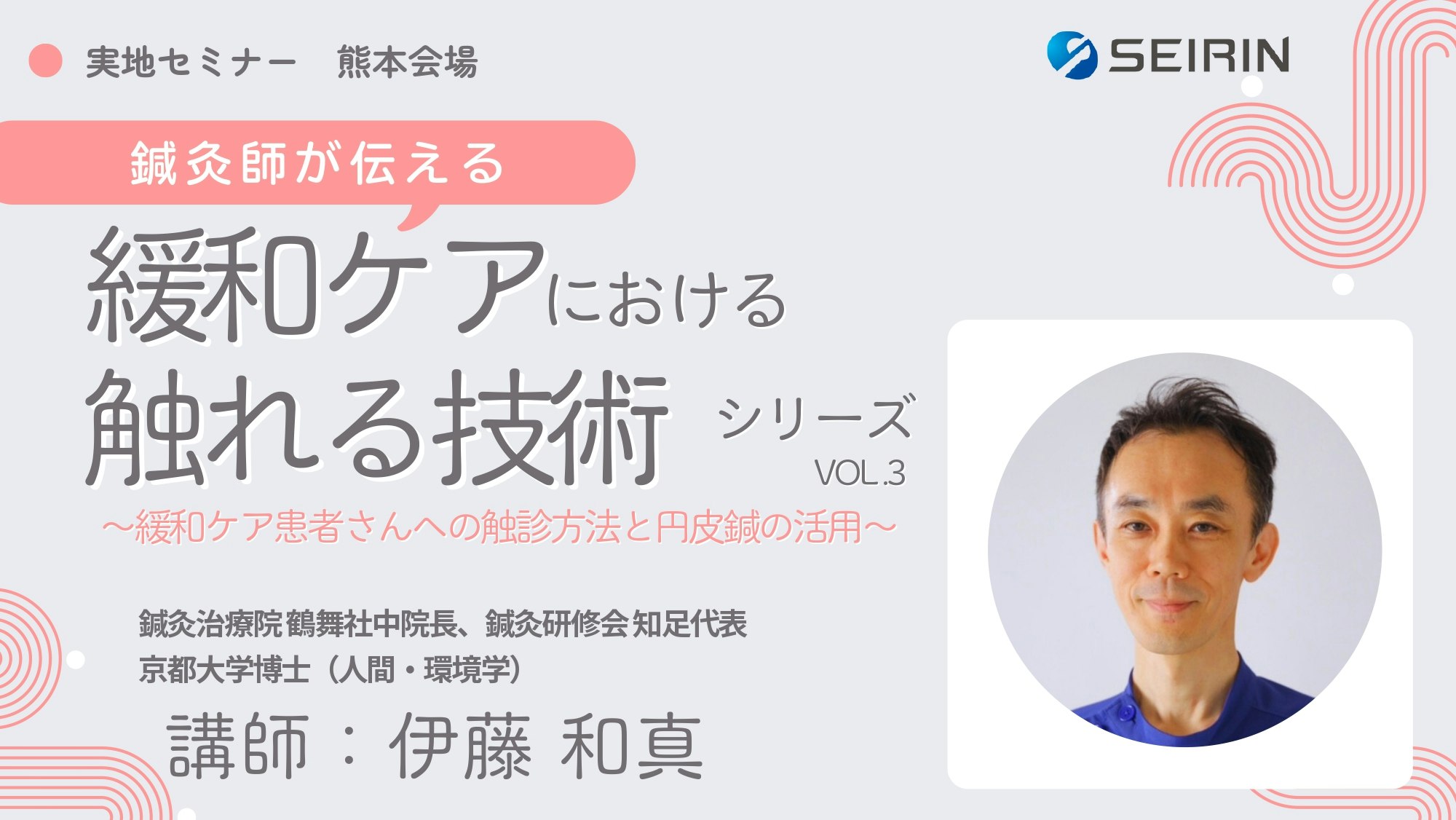はじめに:痛みは「記憶される」ことがある
「もう治っているはずなのに、なぜ痛みが続くのか?」
この疑問に答える鍵は、“疼痛記憶(pain memory)”という神経メカニズムにあります。
疼痛記憶とは、痛みの刺激が何度も繰り返された結果、脳内で「痛み」という感覚とその情動反応が強固に結びつき、定着してしまう現象です。
この記憶は、脳の特定領域――特に海馬・扁桃体・前帯状皮質・前頭前野などのネットワークで形成されます。
本記事では、こうした「痛みの記憶回路」に対し、鍼灸がどのように介入し、神経機能の再学習を促すのかを解説します。
疼痛記憶の神経基盤|どこで、どう記録されるのか
| 脳領域 | 主な役割 | 疼痛記憶への関与 |
|---|---|---|
| 海馬 | 記憶の一時保存・空間学習 | 痛みと環境の関連記憶を形成 |
| 扁桃体 | 恐怖・不安などの情動処理 | 痛み刺激に対する恐怖条件付け |
| 前帯状皮質(ACC) | 感情的苦痛の統合 | 痛みの不快感・注意の維持に関与 |
| 前頭前野 | 判断・自己制御 | 痛みに対する再評価と抑制調整 |
これらの回路が長期にわたって強化されると、「痛みの記憶」が自己強化的に持続する悪循環に陥ります。
単なる末梢の鎮痛ではなく、中枢での「再記憶抑制」や「認知的再構築」が必要になります。
鍼灸が疼痛記憶に介入するメカニズム
① 海馬・扁桃体ネットワークの神経可塑性を調整
鍼刺激は、百会・神門・太衝などを通じて、迷走神経—視床下部—海馬系回路を調整し、
痛みに伴う情動記憶の強化を抑制すると考えられています。
② 内因性オピオイド系・セロトニン系の再活性化
鍼灸により内因性エンドルフィン、セロトニン、ノルアドレナリン系が刺激されると、扁桃体や前帯状皮質の過剰興奮が抑えられ、痛み刺激に対する情動的反応が緩和されます。
③ 前頭前野の再統合と再評価システムの再起動
痛みが記憶として定着すると、「もう治らないかもしれない」という認知的エラーが生じやすくなります。
鍼灸による前頭前野の活性化は、痛みに対する認知の再構築(再評価)を促し、“痛みにとらわれない思考回路”の形成を助けます。
疼痛記憶と関連する症状・疾患と鍼灸の応用
| 症状・疾患 | 疼痛記憶の特徴 | 鍼灸の目的 |
|---|---|---|
| 線維筋痛症 | 無害刺激でも痛い=感覚誤学習 | 情動系の過敏性抑制と再学習 |
| 複合性疼痛症候群(CRPS) | 外傷後に痛み記憶が固定化 | 扁桃体—海馬連関の沈静化 |
| 交通事故後の慢性痛 | トラウマ記憶と痛みの同時固定 | 百会・神門でストレス回路を調整 |
| 医療恐怖・慢性腰痛 | 「動くと痛い」という誤学習 | 認知再評価と脳報酬系の再起動 |
使用される主な経穴とその意図
| 経穴 | 主な作用 |
|---|---|
| 百会(ひゃくえ) | 海馬・前頭前野を中心とした中枢抑制系の活性 |
| 神門(しんもん) | 扁桃体・自律神経の安定化、情動系の沈静 |
| 太衝(たいしょう) | 前頭葉—辺縁系の情動調整、怒りや緊張の緩和 |
| 足三里(あしさんり) | 身体感覚の再教育、痛みと注意の切り離し |
| 内関(ないかん) | 恐怖条件づけの緩和、迷走神経刺激の導入点 |
臨床応用と注意点
- 疼痛記憶は認知・情動・行動の多要因で維持されるため、単回の施術では不十分
- 心的外傷やパニック反応が関与する場合は、心理士・精神科医との併診体制が望ましい
- 初期は「安全な刺激経験」を積み重ね、痛みからの学習の“上書き”を目指すことが重要
まとめ
疼痛記憶とは、単なる神経伝達ではなく、「痛みを感じる脳」が作る神経的な“習慣”です。
鍼灸は、身体感覚の再教育だけでなく、情動系・認知系・報酬系ネットワークを再調整することで、痛みの固定記憶からの“離脱”を支援します。
今後は、HRVや脳波を用いた可視化フィードバックと併用した神経心理的アプローチ型鍼灸の発展が期待されます。