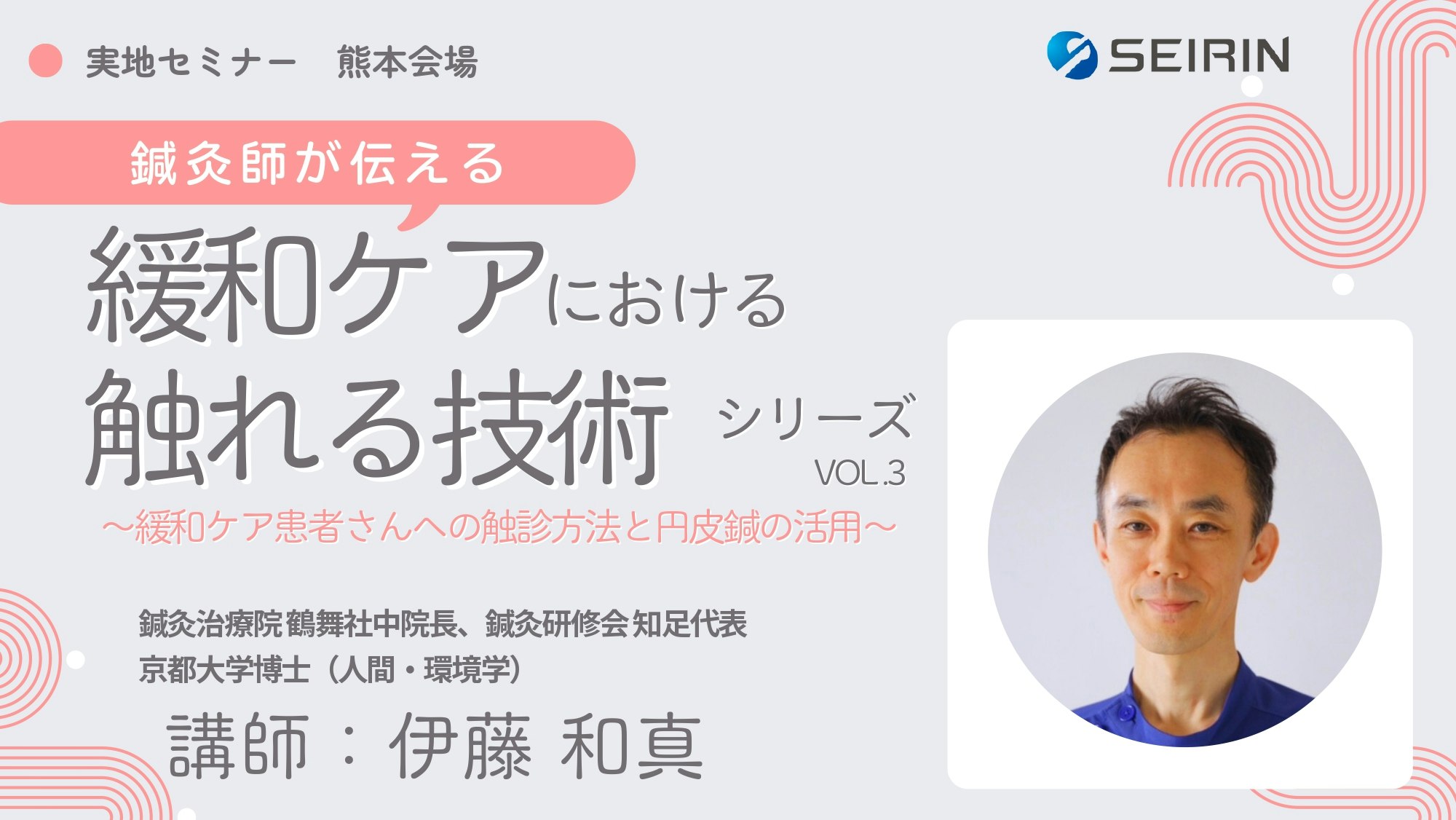はじめに:痛みは脳で制御されている
鍼灸による鎮痛効果は、単なる局所作用では説明できません。とくに近年注目されているのが、中枢神経系における「下行性疼痛抑制系(Descending Pain Inhibitory System)」の関与です。
このシステムは、脳幹部から脊髄後角へと向かう神経ネットワークで構成され、痛覚の「フィードバック制御」機構として機能しています。
鍼灸刺激がこの抑制系を活性化することで、内因性オピオイド(身体のモルヒネ様物質)の分泌が促され、全身的な鎮痛がもたらされるのです。
本記事では、下行性疼痛抑制系の生理学的構造と、鍼灸刺激による活性化機序を解説します。
中枢からの痛覚制御とは
痛みの伝導路は末梢から脳へと一方向に流れるだけではありません。
脳からも脊髄へ向けて、痛覚情報を調整・抑制する神経回路が存在します。これが「下行性疼痛抑制系」です。
この抑制系は、以下の主な中枢部位で構成されます:
- 視床下部(hypothalamus)
→ 情動・自律神経・ホルモンと痛みの統合調整を担う - 中脳水道周囲灰白質(PAG:periaqueductal gray)
→ オピオイド受容体が高密度に分布し、痛覚制御の司令塔 - 延髄網様体・大縫線核(RVM)
→ セロトニンやノルアドレナリンによる調節性の投射系
これらの中枢から脊髄後角に向けて抑制性神経投射が行われ、痛覚情報の感受性が抑えられることで、「痛みの制御」が実現します。
内因性オピオイドの役割
この抑制系を作動させる鍵となるのが、「内因性オピオイド」です。
これは、モルヒネと同様の鎮痛作用を持つ、身体内で合成・放出される神経ペプチド群で、代表的なものに以下が挙げられます:
- エンドルフィン(β-endorphin)
- エンケファリン(met-・leu-enkephalin)
- ダイノルフィン(dynorphin)
これらは、PAGやRVM、脊髄後角に分布するオピオイド受容体(μ, δ, κ)に結合し、神経伝達物質の放出を抑制することで鎮痛を発揮します。
鍼刺激による下行性抑制の活性化
鍼刺激は、末梢の感覚入力を通じて、中枢の疼痛抑制ネットワークを活性化します。
刺激は以下のような経路をたどります:
- 皮膚・筋層の感覚受容器を刺激(Aδ・C線維)
- 脊髄後角を介して、PAGに上行
- PAGでオピオイドが放出 → RVMを経て下行性入力が促進
- 脊髄後角のニューロン活動が抑制され、痛みの感受性が低下
このように、鍼刺激は末梢の「入力」から中枢の「制御回路」までを通じて、痛みを下流でブロックする働きを持ちます。
また、電気鍼(EA)ではこの系の活性がより顕著とされ、鎮痛効果の持続時間が延長するという報告もあります。
痛みの多層的制御における位置づけ
下行性疼痛抑制系は、急性痛・慢性痛・ストレス性疼痛などのさまざまな局面に関与しています。
また、ゲートコントロール理論と補完的に働き、局所と中枢の両面から疼痛抑制が実現されます。
一方で、抑制系そのものの機能が低下している(うつ病・線維筋痛症など)ケースでは、鍼灸刺激がその再活性化を誘導する補助療法として注目されています。
鍼灸臨床への応用と説明の工夫
患者に対して鍼灸の鎮痛作用を説明する際、
- 「脳の中に痛みを下げるスイッチがあり、鍼がそれを押す役割をします」
- 「身体に備わったモルヒネ様物質(オピオイド)を自前で出すしくみがあります」
といった表現を使えば、生理学的な根拠を持ちながらもわかりやすい説明が可能です。
教育現場でも、鍼灸効果を機能解剖学的に説明する一例として、下行性抑制系の理解は非常に有用です。
関連記事リンク
- 鍼灸師のための生理学総論─恒常性維持と鍼刺激の生理学的理解
- ゲートコントロール理論と鍼灸|痛みの脊髄制御メカニズム
- 慢性痛と中枢感作|神経可塑性の視点
- 視床下部と情動・痛覚調整の関連