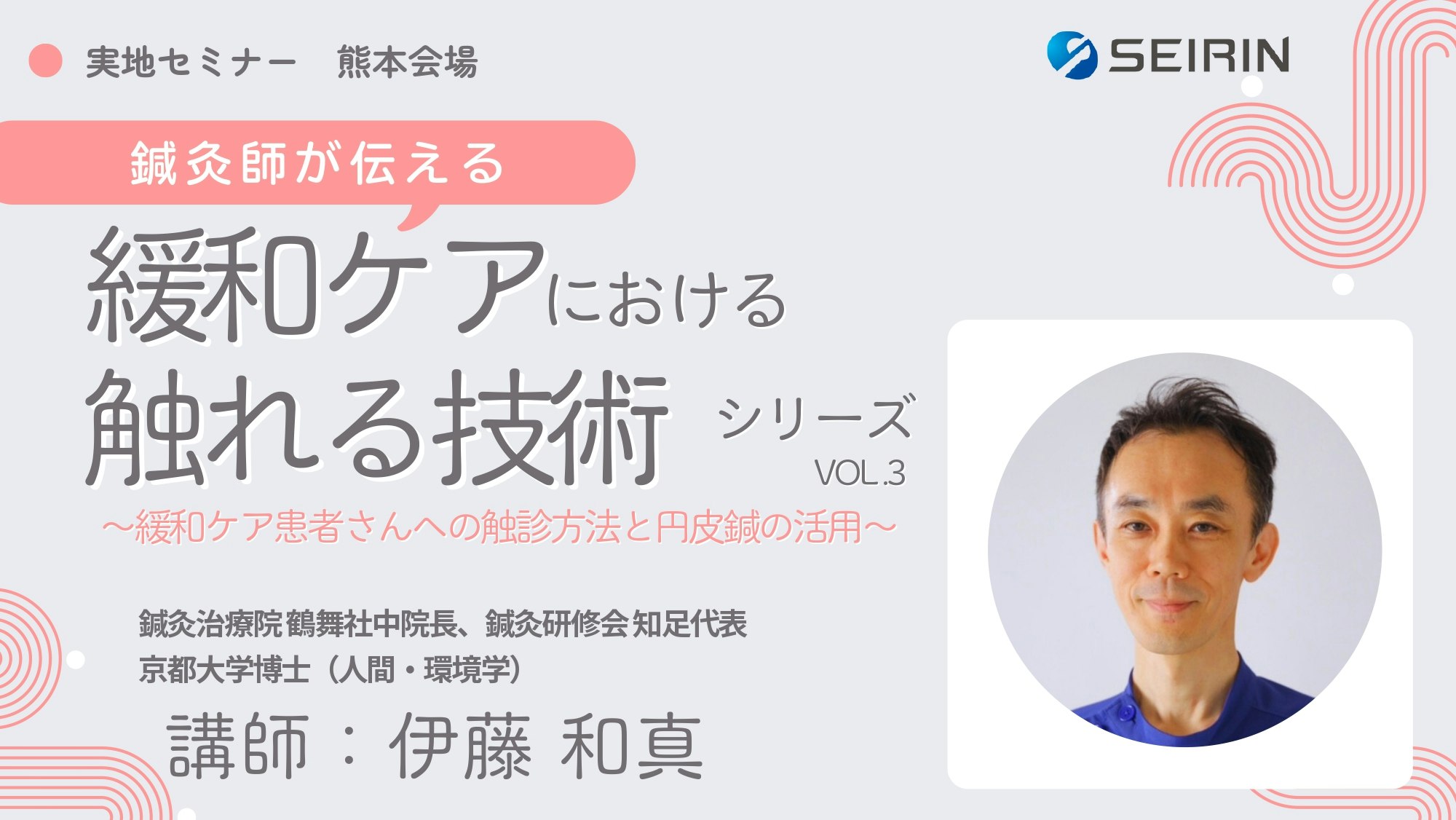はじめに
「血圧が高い」「手足が冷える」「動悸がする」――こうした循環器系のトラブルに対して、薬だけに頼らず、自然な方法で体を整えたいと感じている方が増えています。
近年、鍼灸(しんきゅう)が血圧・血流・心拍変動(HRV)に影響を与えることが明らかになっており、循環器の補完療法として注目されています。
この記事では、鍼灸がどのように心臓や血管に働きかけるのかを、生理学的な視点から詳しく解説していきます。
循環器系の基本と、自律神経との関係
私たちの体は、心臓が送り出す血液によって酸素と栄養を全身に運んでいます。
この循環がスムーズであるためには、心拍・血管の収縮・血液の流れが適切にコントロールされる必要があります。
ここで重要なのが、自律神経の働きです。
| 自律神経の種類 | 役割 |
|---|---|
| 交感神経 | 心拍数を上げる・血管を収縮させる(=緊張・戦闘モード) |
| 副交感神経 | 心拍数を下げる・血管を拡張させる(=リラックス・回復モード) |
現代人はストレス過多により交感神経が優位になりがちで、これが高血圧・冷え・動悸などの原因になるのです。
鍼灸が循環器系に働く3つの仕組み
① 迷走神経刺激による心拍調整(HRVの改善)
鍼灸は、迷走神経(副交感神経)を刺激し、心拍を整えることができます。
特に、百会・内関・神門・耳介のツボは、迷走神経を介してHRV(心拍変動)を増加させ、リラックス状態を促進します。
HRVとは、心拍の揺らぎのことで、高いほど自律神経の柔軟性が保たれている証拠。
低HRVの人は、慢性的なストレスや高血圧のリスクが高い傾向にあります。
② 一酸化窒素(NO)を介した血管拡張作用
鍼灸刺激は、皮膚・筋肉レベルの神経終末を通じてNO(一酸化窒素)という血管拡張物質の放出を促します。
NOは、血管平滑筋をゆるめて血管を広げ、血圧を自然に下げる作用があります。
このメカニズムは、以下のようなツボで確認されています:
- 足三里・三陰交:下肢の血流促進、末梢循環の改善
- 合谷・太衝:上肢・顔面の血流、末梢血管の調整
③ 交感神経の過緊張をゆるめる
現代人は、ストレス・睡眠不足・スマホ使用などで交感神経が常に活性化しています。
鍼灸は、この過緊張を鎮め、副交感神経とのバランスを整えることで、心臓や血管への負担を軽減します。
たとえば、夜間の動悸・寝つきの悪さ・緊張性の血圧上昇などは、鍼灸で症状が軽くなることがあります。
鍼灸が有効とされる循環器の症状例
| 主な症状 | 鍼灸による期待効果 |
|---|---|
| 高血圧(本態性) | NO放出による血管拡張、自律神経の調整 |
| 動悸・期外収縮 | 迷走神経刺激による心拍リズムの安定化 |
| 冷え性・末梢循環障害 | 末梢血流の改善、血管拡張 |
| 睡眠中の高血圧 | 副交感神経の賦活による夜間血圧低下 |
| ストレス性高血圧 | HRVの改善、自律神経バランスの回復 |
※注意:狭心症や心不全など、器質的な心疾患では、医師の診断と治療が優先されます。
よく使われるツボとポイント
| 経穴名 | 特徴と作用 |
|---|---|
| 内関(ないかん) | 心包経、動悸・胸部不快感の改善に用いる |
| 神門(しんもん) | 心経、ストレス性高血圧・不眠に適応 |
| 足三里(あしさんり) | 胃腸+末梢血流の調整に有効、冷え対策にも |
| 合谷(ごうこく) | 血流調整・自律神経バランスを整える |
| 太衝(たいしょう) | 肝気上逆タイプの高血圧・緊張緩和に用いる |
鍼灸を受ける際の注意点(循環器疾患と併用時)
- 降圧薬を服用している方は、施術後の血圧低下に注意が必要です。
- 心臓ペースメーカー装着中の方は、電気鍼(パルス)を避け、通常鍼のみで対応します。
- 抗凝固薬(ワーファリンなど)服用中の方は、出血リスクを避けるため、施術部位を厳選します。
まとめ
鍼灸は、心臓・血管・自律神経の連携にやさしく働きかけることで、薬に頼りすぎず循環機能を整える補完医療として注目されています。
特に高血圧・冷え・ストレス関連の循環器トラブルには、迷走神経刺激・NO放出・HRV改善といった多面的な効果が期待されます。
生活習慣と併せて、鍼灸の活用を検討してみてください。