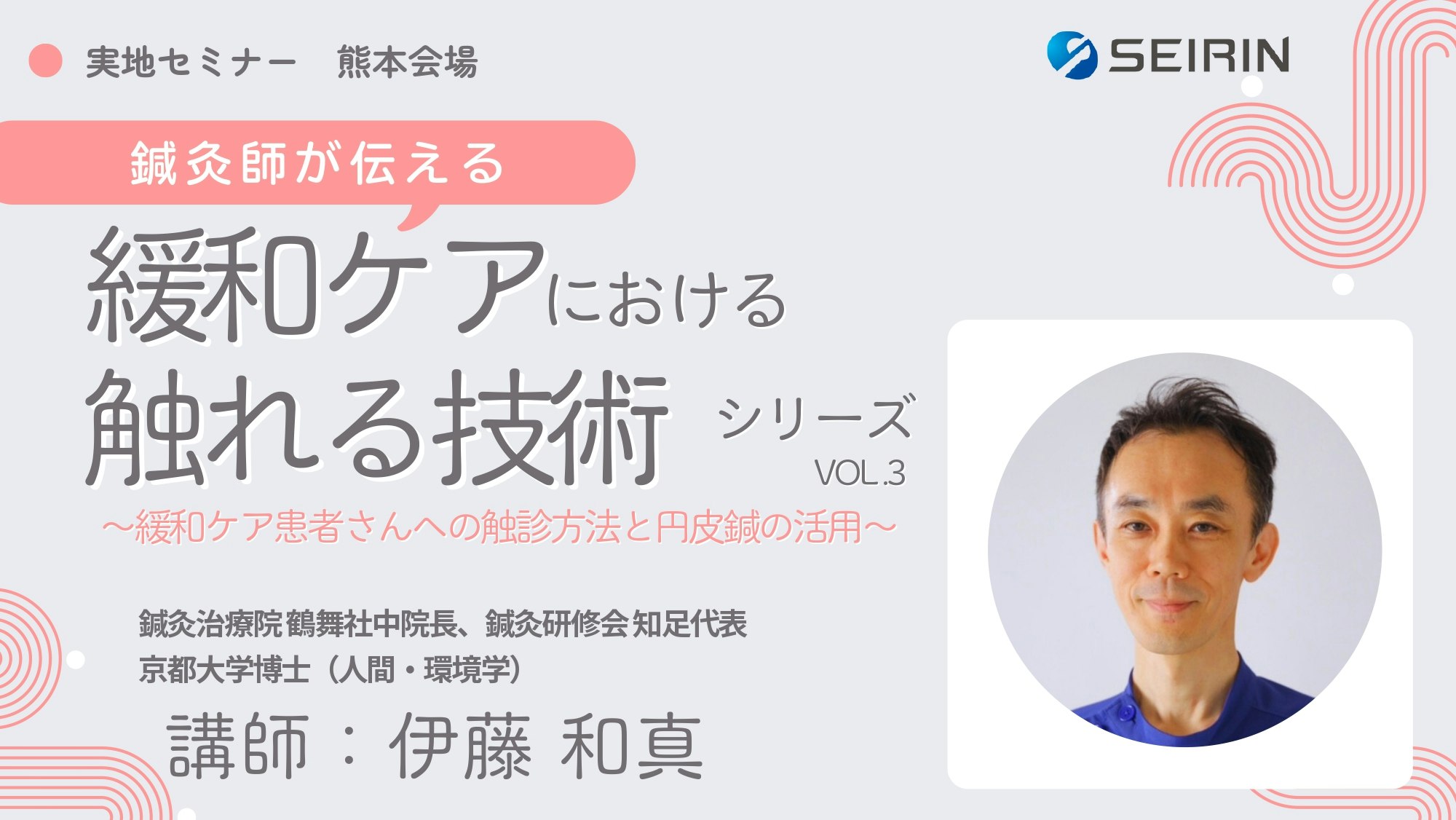はじめに
「疲れやすい」「よく眠れない」「なんとなくイライラする」――
こうした症状が続いているとき、単なるストレスではなく、ホルモンバランスの乱れ(内分泌異常)が関係している可能性があります。
ホルモンは、身体の働きを全体的にコントロールする重要な“指令物質”です。
そして近年、鍼灸による神経—内分泌の調整作用が注目され、ストレス性疾患や更年期症状、月経不順などへの補完療法として応用が進んでいます。
本記事では、鍼灸がホルモンの働きにどう影響するのかを、内分泌生理の基礎から丁寧に解説します。
ホルモンとは?内分泌系の基本をおさらい
私たちの体内には、脳・甲状腺・副腎・膵臓・卵巣(精巣)など、ホルモンを分泌する“内分泌腺”が存在します。
そこから分泌されるホルモンは、血流に乗って全身をめぐり、各臓器に「働け」や「休め」といった指令を送ります。
内分泌系の中枢にあるのが、視床下部と下垂体という脳の一部です。
この中枢が正しく機能していれば、以下のようなバランスが維持されます。
- 睡眠リズム(メラトニン、セロトニン)
- ストレス対応(コルチゾール)
- 月経周期(エストロゲン、LH、FSH)
- 血糖調節(インスリン、グルカゴン)
- 体温調整・代謝(甲状腺ホルモン)
逆に、ストレスや加齢、睡眠不足などの要因でこれらの働きが崩れると、自律神経や免疫系も巻き込んで体全体が不調になることがあります。
鍼灸がホルモン分泌に与える3つのアプローチ
① HPA軸(視床下部-下垂体-副腎)への作用
強いストレスを感じたとき、脳は「危険だ!」と判断して、副腎からコルチゾールというホルモンを放出します。
この反応は必要ですが、慢性的に続くと免疫低下・うつ状態・不眠を引き起こします。
鍼灸は、視床下部に間接的に働きかけ、コルチゾール分泌の調整をサポートします。
結果として、ストレスホルモンの過剰状態を和らげ、体の回復モードを促進します。
② 自律神経調整を通じた内分泌の安定
ホルモン分泌は自律神経の支配も受けています。
たとえば、睡眠ホルモン「メラトニン」は、副交感神経が優位にならないと分泌されません。
鍼灸は、百会・内関・神門などを刺激することで副交感神経の活動を高め、睡眠の質やストレス応答に関わるホルモンバランスを整えることが可能です。
③ 卵巣・甲状腺・膵臓への間接的サポート
東洋医学では「肝」や「腎」のバランスが月経や妊孕性(にんようせい)に関与するとされますが、これは現代医学でいうエストロゲンやプロゲステロンの変動と対応しています。
特に以下のようなホルモンの不調に対して、鍼灸が活用されています。
- 月経不順・無月経 → 性腺ホルモンの分泌調整
- 更年期障害 → エストロゲン低下への補完
- 甲状腺機能の異常 → 自律神経を介してT3・T4の過不足を緩和
- 糖尿病予備群 → インスリン感受性の改善をサポート
鍼灸が適応となる内分泌関連の症状
| 症状・疾患名 | 鍼灸の補完的役割 |
|---|---|
| ストレス・過労 | コルチゾール分泌の抑制と副交感神経優位化 |
| 不眠・浅い眠り | メラトニン分泌促進、交感神経抑制 |
| 更年期障害 | ホルモン変動に伴う不定愁訴の軽減 |
| 月経不順・無月経 | FSH・LHの分泌調整サポート |
| 甲状腺機能異常(バセドウ病・橋本病など) | 自律神経・免疫の過反応の緩和 |
よく使われる経穴と意味
| ツボ名 | 効果の概要 |
|---|---|
| 百会(ひゃくえ) | 自律神経の安定、ホルモン中枢の調整に関与 |
| 神門(しんもん) | ストレス反応の緩和、心拍と副交感神経の調整 |
| 三陰交(さんいんこう) | 婦人科症状、月経不順、更年期に使用頻度高い |
| 中極(ちゅうきょく) | 下腹部臓器(子宮・膀胱)の調整、冷えの改善 |
| 足三里(あしさんり) | 全身の調整、胃腸機能とストレス性疲労の軽減 |
鍼灸を受けるときの注意点
- ホルモン治療中(ピル、甲状腺薬、糖尿病薬など)の方は、医師との連携が重要です。
- 急性ホルモン疾患(バセドウ病の活動期など)では、刺激量や部位に注意が必要です。
- 妊娠中は刺鍼禁忌部位を避け、専門的な妊婦対応が可能な鍼灸師に相談しましょう。
まとめ
ホルモンバランスの乱れは、身体と心の健康に大きな影響を与えます。
鍼灸は、視床下部—下垂体—副腎という内分泌中枢にやさしく働きかけることで、薬に頼らずホルモンの過不足を整える選択肢となり得ます。
不調の根本にアプローチしたい方、ホルモンの変動に伴うつらさを自然に緩和したい方は、鍼灸治療をぜひ検討してみてください。