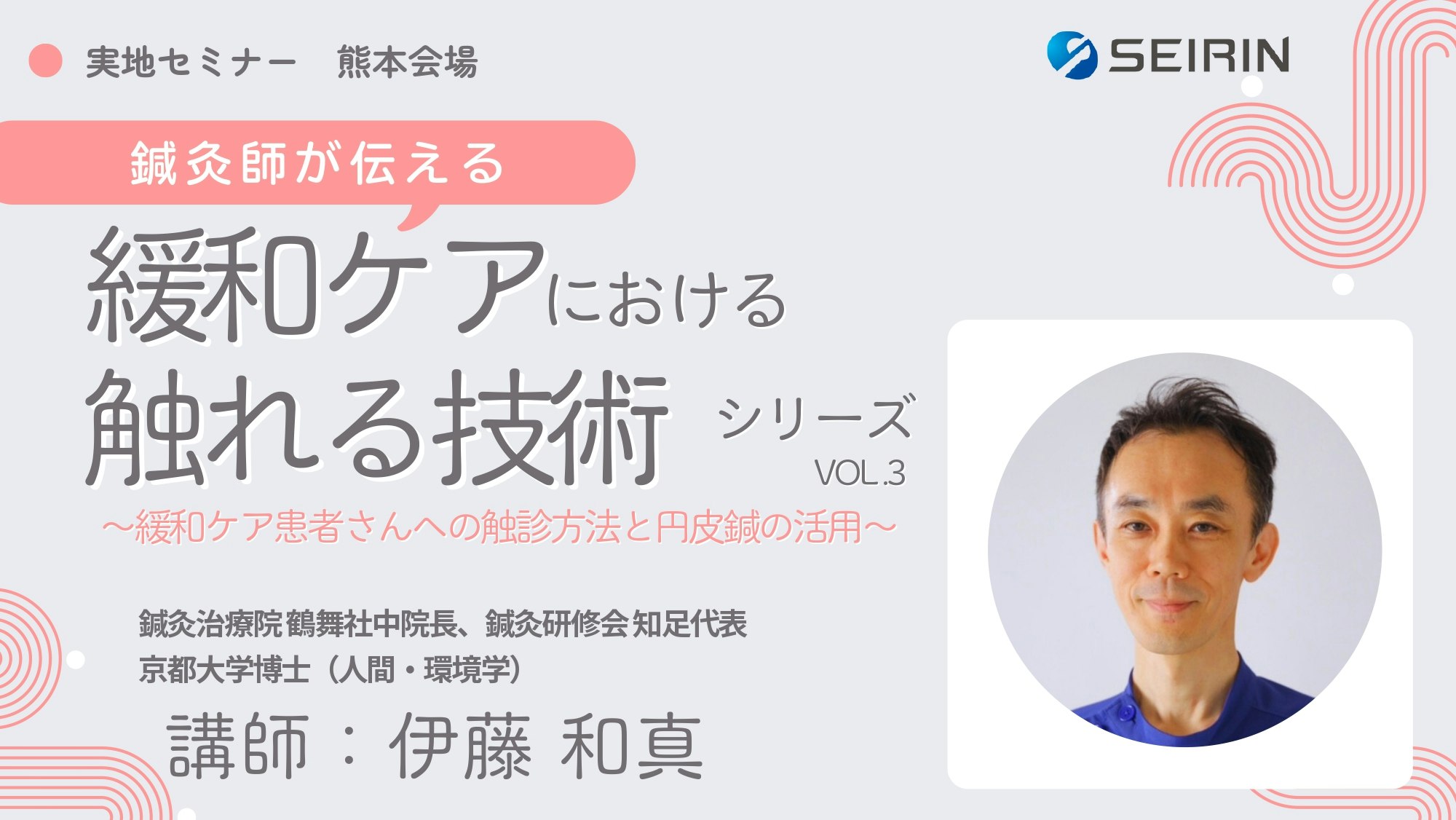はじめに:もうひとつの「神経」の主役
脳や脊髄の機能といえば「ニューロン(神経細胞)」を思い浮かべがちですが、実は中枢神経系の約半分はグリア細胞(神経膠細胞)が占めています。
このグリア細胞は、単なる「神経のサポーター」ではなく、情報伝達・炎症反応・神経可塑性に深く関与する積極的な調整者です。
近年、慢性痛・うつ病・自律神経障害の背後に、グリア細胞の異常活性=神経炎症が関与することが明らかになってきました。
本記事では、鍼灸がこのグリア細胞の機能異常にどう働きかけるかを、生理学的に掘り下げていきます。
グリア細胞とは?|種類と役割の整理
グリア細胞には主に3種類があり、それぞれが異なる働きを担っています。
| 細胞名 | 機能 | 過剰活性時の影響 |
|---|---|---|
| アストロサイト | 神経栄養・血液脳関門維持・代謝補助 | グルタミン酸蓄積 → 興奮毒性・慢性痛 |
| ミクログリア | 中枢免疫担当・異物処理 | サイトカイン(IL-1β, TNF-α)放出 → 神経炎症 |
| オリゴデンドロサイト | ミエリン形成(伝導速度の維持) | 損傷時の修復遅延・神経伝達障害 |
とくにミクログリアとアストロサイトは、慢性疼痛やうつ症状、認知機能障害の維持因子として注目されています。
鍼灸がグリア細胞に作用する3つのメカニズム
① ミクログリアの炎症性サイトカイン産生を抑制
鍼刺激により、迷走神経—副腎経路の活性化を介して、ミクログリアからのTNF-α・IL-6・IL-1β産生が低下。
特に、百会・神門・足三里などの経穴刺激でこの反応が誘導されやすいことが、動物モデルで示唆されています。
② アストロサイトのグルタミン酸代謝を調整
アストロサイトは、神経間隙からのグルタミン酸を回収する役割を持ちますが、過剰なストレスで機能低下を起こすと、興奮毒性による神経損傷や慢性痛が生じます。
鍼灸は、脊髄レベルでのグルタミン酸輸送体(GLT-1)の発現を上げ、アストロサイトの正常化を促進することが報告されています。
③ GABA系・内因性オピオイド系の再活性化
グリア細胞の活性化により抑制性系(GABA、エンドルフィンなど)が弱まり、中枢抑制ネットワークの働きが落ちることが慢性疼痛や不安症の温床になります。
鍼灸刺激は、これら抑制系の再活性化を促し、グリア細胞が誘導する神経過敏状態を緩和する補助的作用を持ちます。
臨床応用とグリア細胞の関与が考えられる症状
| 症状・疾患 | グリア細胞の関与 | 鍼灸の目的 |
|---|---|---|
| 慢性疼痛(腰痛・肩こり) | ミクログリアの持続活性 | 中枢感作抑制・炎症制御 |
| 線維筋痛症 | アストロサイトの興奮性過剰 | 痛覚閾値上昇と情動安定 |
| うつ病・不安障害 | 神経炎症とセロトニン代謝低下 | 扁桃体・海馬の炎症抑制 |
| 認知機能低下(MCI) | ミクログリアの慢性活性化 | 脳血流と神経栄養因子の維持 |
使用される主な経穴とその意図
| 経穴名 | 主な作用 |
|---|---|
| 百会(ひゃくえ) | 中枢抑制の統合点、海馬・前頭葉の調整 |
| 神門(しんもん) | 情緒安定、迷走神経刺激、炎症反応抑制 |
| 足三里(あしさんり) | 全身免疫と抗炎症、内因性オピオイド誘導 |
| 合谷(ごうこく) | 脊髄後角の過敏性低下、神経伝導制御 |
| 太衝(たいしょう) | 前頭前野—扁桃体軸の抑制、怒り・焦燥の緩和 |
注意点と施術上の留意事項
- 自己免疫疾患・脳炎後遺症・神経変性疾患では、過剰な刺激が炎症を悪化させる場合もある
- グリア細胞は慢性刺激に対し二相性(保護/破壊)の性質を持つため、過剰介入は避け、漸進的施術が基本
- 神経疾患に対しては、神経内科や精神科との併診・連携体制が望ましい
まとめ
グリア細胞は、これまで見過ごされてきた「第3の主役」であり、鍼灸はその機能異常に対する新たな介入手段です。
迷走神経刺激・脳内抑制ネットワークの再調整・サイトカイン抑制などを通じて、慢性痛・情動障害・神経炎症に対し多面的なアプローチが可能です。
鍼灸は単なる痛み止めではなく、神経系全体の恒常性維持を助ける“調整医療”として進化を続けています。