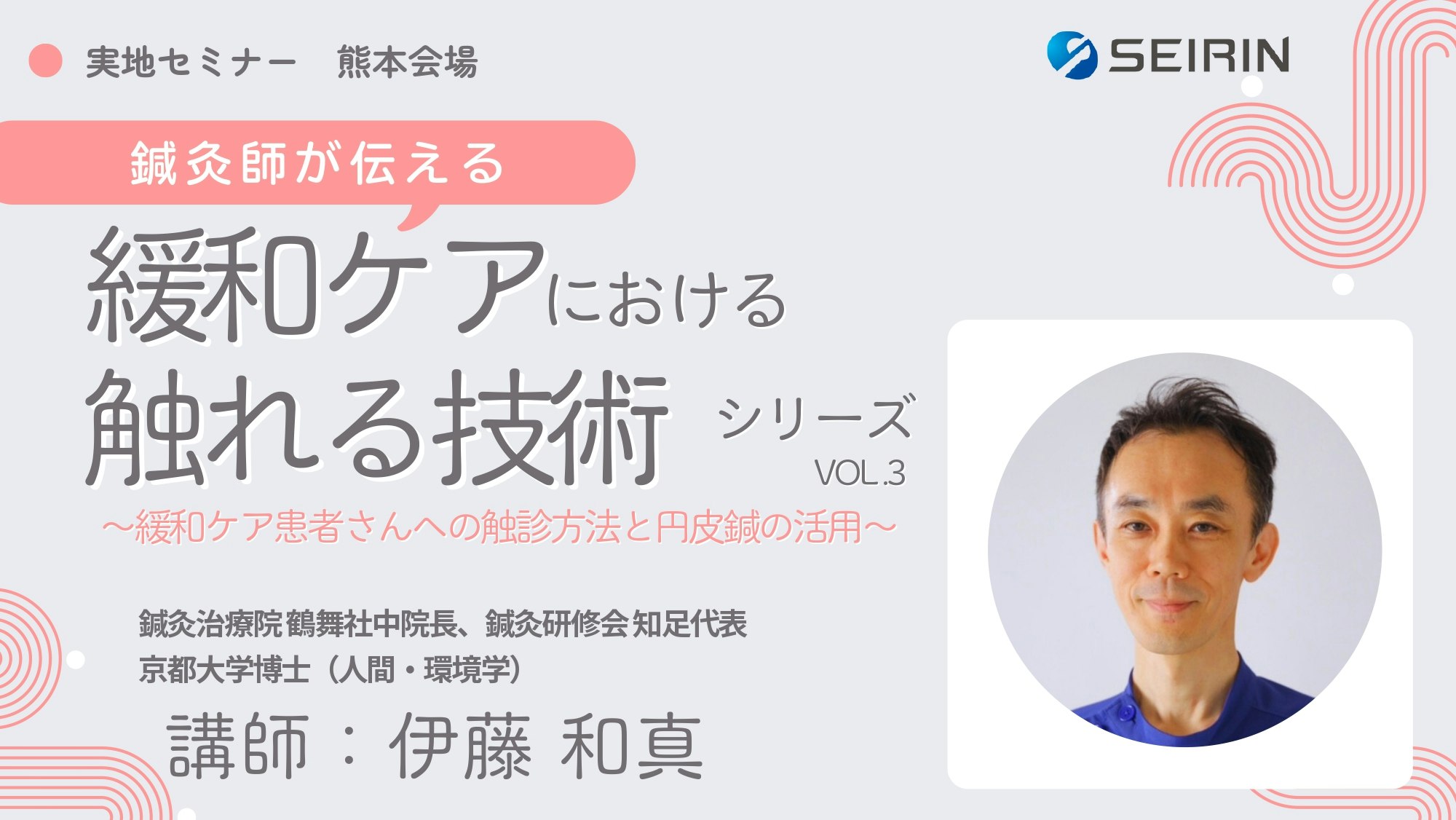はじめに
「鍼灸で痛みが和らぐのはなぜ?」――
その問いに対して、もっともよく知られている科学的説明が、ゲートコントロール理論(Gate Control Theory)です。
1965年にMelzackとWallによって提唱されたこの理論は、痛みは単なる末梢の反応ではなく、脊髄と脳で“調整される感覚”であることを示しました。
鍼灸は、このゲートを操作する“鍵”として働く可能性があります。
この記事では、痛みの伝達経路と鍼灸による抑制メカニズムを詳しく解説します。
ゲートコントロール理論とは?
痛みの信号は、以下の経路を通じて脳に伝わります:
- 末梢受容器(侵害受容器)が刺激を感知
- Aδ線維やC線維が脊髄後角に信号を送る
- 脊髄後角での中継・調整を経て、視床・大脳へ伝達
この時、脊髄後角にある「痛みゲート」が開くと痛みを感じ、閉じると痛みが抑えられます。
- Aβ線維(触覚・圧覚)の活動が高まると、ゲートが閉まりやすくなる
- C線維(鈍痛)の入力が多いと、ゲートが開きやすくなる
この仕組みを利用して痛みをコントロールするのがゲートコントロール理論です。
鍼灸による痛みゲート制御のメカニズム
① Aβ線維を介した抑制性介在ニューロンの活性化
鍼刺激(特に浅刺・雀啄法・経皮的電気鍼など)は、Aβ線維を活性化し、脊髄後角にある抑制性介在ニューロンを興奮させます。
これにより、C線維からの痛覚信号が遮断され、脳への伝達が減弱します。
② 内因性オピオイドの放出
鍼刺激は、中脳—延髄—脊髄に至る下行性抑制系を活性化させ、以下の内因性鎮痛物質が放出されます:
- エンドルフィン
- エンケファリン
- ダイノルフィン
これらは、脊髄後角および中枢レベルで痛みの伝達をブロックします。
③ 視床—帯状回—前頭前野の情動痛処理の調整
慢性痛では、「感覚としての痛み」だけでなく「不快感・苦しさ」が問題になります。
鍼灸刺激は、視床や前帯状回(ACC)などの活動を調整し、痛みに対する情動反応を緩和することが示唆されています。
臨床で見られるゲートコントロール応用例
| 症状 | 鍼灸の作用とポイント |
|---|---|
| 慢性腰痛 | Aβ線維刺激で痛覚をブロック+深層筋のスパズム除去 |
| 緊張型頭痛 | 頭頚部の圧刺激によるゲート遮断+筋緊張の緩和 |
| 関節痛(変形性膝関節症など) | 経皮電気刺激で痛覚調整+歩行時痛の軽減 |
| 筋筋膜性疼痛症候群(MPS) | トリガーポイント刺鍼で局所ゲート制御と中枢抑制を同時に |
よく使われる経穴と刺激法
| 経穴 | 意図 |
|---|---|
| 阿是穴 | 局所のトリガーポイントに対応、Aβ線維刺激に最適 |
| 陽陵泉 | 膝関節周囲の痛みに頻用、経絡と筋膜両面からアプローチ |
| 合谷 | 全身鎮痛の調整点、特に顔面・上肢への投射に有効 |
| 太衝 | 情動性の痛み、不安・怒りと連動する疼痛に適応 |
| 電気鍼(経皮電気刺激) | Aβ線維の活性化を目的に低頻度(2Hz)で使用されることが多い |
注意点
- 急性外傷や炎症性疾患(熱感あり)には、ゲート理論に基づく鍼刺激は逆効果となることがある
- 慢性疼痛・情動性疼痛には、中枢抑制・情動調整との併用が重要
- 電気鍼や強刺激は、高齢者・神経過敏体質では副交感神経優位になりすぎる可能性あり
まとめ
ゲートコントロール理論は、鍼灸による鎮痛作用の基礎生理を説明する重要な理論的枠組みです。
Aβ線維の刺激・抑制ニューロンの活性化・内因性オピオイドの誘導など、鍼灸は神経系に対して多段階の調整を行うことが可能です。
とくに慢性痛やストレス性疼痛では、感覚・情動・認知すべての側面に働きかける鍼灸の統合的効果が期待されます。